この本を手にとったのは子供が1歳になる頃です。なんだかその頃は慣れない子育てに疲れ切っていたような記憶があります。
図書館で手に取った本
今日のレビューは「子育てハッピーアドバイス」です。
この本は初めての事ばかりの育児で疲れていたときに偶然図書館で見つけて読みました。
子供が1歳になりよちよちと歩き始めて目が離せなくなった事、夜の寝かしつけがうまくいかなくて寝不足だった事、しつけってどうすればいいのか悩んでいた事・・・など。
その頃は慣れない子育てで悩みが山のように溢れてきていました。
子育てを楽しみたい気持ちもあるけれど、夫は忙しくてひとりで育児のほとんどを背負っていた事で押しつぶされそう。
楽しそうに子育てをする友人の話を聞いて、自分はダメな母親だなぁ・・・と比べて落ち込んでばかりいました。
この気持ちをなんとかしたくて、たくさんある育児関係の本の棚の中から読みやすそうなものを手に取りました。
育児疲れの母親には難しい・詳しい本より、今欲しい言葉を
その時の私には難しそうな本や詳しく説明されているような本を手に取る余裕はなかったです。夜泣きに疲れて眠かったんです。
ネットで調べるのは時間もかかるし正解を見付けにくい
どうすればいいのか悩む⇒ネットで検索して答えを探す⇒いろんな人がいろんな事を書いているので結局良く解らなくなる⇒解決しないまま寝不足が加速。
最近は簡単に情報が手に入る分、情報がたくさんありすぎて迷うのも問題ですね。
人それぞれ考え方が違うので、Aかな?それともBのほうが子供にとって良いことなのかな?といろんな意見に振り回されてしまいます。
子供のタイプにもいろいろあるしね。
子育てハッピーアドバイスはほとんどイラストとマンガ
子育てハッピーアドバイスはほとんどイラストとマンガです。
目次を見て、今の自分に必要だと思うページだけをサッと開いて読むと、悩んでいたことの答えがパッと理解できるようになっています。
子供に振り回されていても、眠くてフラフラでも、時間が無くても大丈夫。
読むと「大丈夫だよ。あなたはよく頑張っているよ」と言ってもらえて、心が軽くなるんです。
ちょっと子供のことを見ただけで言われる「こうすればいいのに」「もっとこうしたら?」というアドバイスはもうお腹いっぱいなんです。
うまくできていないことも自分が一番解ってるんです。
実生活では誰も言ってくれないけれど、精一杯慣れない子育てを頑張っていることを誰かに認めてもらいたいんですよね。
そういう苦しい子育てしているお母さんにぜひおすすめしたいです。
子供には叱っていい子といけない子がいる
この本は発達障害関連の本ではありません。
でも、本の中では発達障害に関連しそうなキーワードがたくさん出てきます。特に「自己評価を育むこと」。
発達障害児は怒られる機会が多く、自己評価が下がりがち
自己評価が下がってしまうと、後々いろんな問題が出てきてしまうそうです。これが、鬱や引きこもりなどの2次障害です。
この本では自己評価の育み方がいろんな場面で出てきます。
親だったらやってしまいがちな間違った怒り方がわかりやすく書かれているので、自分のいつもの行動に照らし合わせてみることができます。
わたしも「あー、これは言っちゃうなぁ・・・」という反省点がたくさんありました。
そして、それ以上に「あ、私は見事に悪い例のほうのみで育てられてるわ」という恐ろしいことに気付いたのです。
うちの母はことあるごとに「こうしたら?昔はこうしたものよ?」とアドバイスしてくるタイプの人です。
自分が子供の頃から言われていた言葉、怒られ方、しつけの方法・・・。どれをとってもほとんどが「こうするべきではありません」と理由とともに書かれていました。
そうか!だから私の自己肯定感は皆無といっていいほど低いんですね。気付けてよかった。
この本を読まなかったら、私は自分が育てられたようにわが子も育てていたでしょう。
昔はみんなそんな感じでしつけられていたんだろうし、母親も私と同じように子育てに悩みながら育ててくれたんでしょう。
もう済んだことだし今更仕方ないよね。親も被害者なのかもしれません。
負の連鎖は私が断ち切ろうと思える
私にできることは、自分が育てられたようには育てないという事のみです。
特に、本の中で紹介されている「叱っていい子といけない子」の部分を読むと、うちの子はどう考えても「叱るのに注意が必要な子」のほうです。
なんとか、子供は自己評価を下げないように育ててあげたいなぁ。
できるだけ、否定しないように言葉を選んで接しているつもりですが、それでも悪戯ばかりしていう事を聞かないときなどほんとに困ったときは自分が言われて育った方法をつい取ってしまいそうになります。
あぁ、親もこんな気持ちだったんだなぁ・・・。
大好き、怒っちゃってごめんねと子供を抱きしめながら、なんだか自分の子供の頃のことを思い出したりしています。
「あのとき親も私のことが嫌いで言ってた訳じゃない」と解る年齢にやっとなったのかもしれません。
母親のサポートとウチでの活用方法
子育てハッピーアドバイスのシリーズはかなりたくさん出ています。
私は1から3までしか読んでいませんが、結構なページを割いて「母親へのサポート」について書かれています。
子育てハッピーアドバイスはお父さんにもおすすめ
母親はずっと前から母親だった訳ではなく、子供を産んで母親になるのです。最初っから全てを上手にできる訳ではないし、完璧なはずがありません。
悩みながら子供と一緒に成長していってお母さんになるんです。
子育てハッピーアドバイスでは、どれだけ母親が大変なのか・頑張っているのかから始まって、父親や祖父母がどう母親をサポートしていけばいいのかということも書かれています。
なので、どうやって子育てに参加したらいいのか解らないお父さん達には特におすすめ。「忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス」という本まで出ています。
本当はうちの夫もしっかり読んでもらいたいのですが、こういう子育て系の本はまったく読んでくれません。
まぁ、だいたい育児手伝え!と書かれているし、押し付けられた気分になって読みたくもなくなりますよね。
なので、気を付けて欲しいなぁと思ったことがあったら付箋をしてテーブルに乗せておくことにしています。(パパ向けのに付箋を貼られているとイヤミっぽいので、母親向けのに貼ります)
そうすると、夫は「お。今なんか悩んでるのかな?」と思うらしく、パラパラと本をめくることがあるんです。
あと、私は3人の子供を育てた子育てのプロよ!と思っている祖父母にもおすすめです。
状況や時代が変わり、昔の子育ては現在では非常識と言われるものがたくさんあります。ちなみに私が育てられた方法はほとんど今は「こういう風に声かけしてはいけません」と書かれてありました。
昔ながらの方法もいいのですが、男女差別や時代錯誤な考え方が元になっているかもしれません。
また医療も進んでいるので、研究が進んで、昔はOKでも今はダメだということも多いです。ぜひかわいいお孫さんために、自分のやり方ではなく現代のやり方でお手伝いをしましょう。
父親にも子供に合った子育てを知って欲しい
うちの子は不安が強く叱るのに注意が必要なタイプの子供です。
先日、2歳児特有のかんしゃくを起こして大騒ぎしている子供を見ながら夫が言いました。「もっとしっかり叱らないといけないのかな・・・」と。
私は注意の仕方を簡単に説明して、発達障害のある子をきつく叱ることのデメリットを話したのですが、たぶん夫は「今流行りの叱らない子育てか」くらいに思っていそう。
たぶん会社にそういう考えの人がいるので、何度話をしても気付くと同じ思考に戻ってしまうようです。
ゴールデンウィーク中に子供に合った叱り方のページを見てもらえたらいいな。
夫婦で子供への対応方法が違うと、子供も混乱するし声かけの効果も半減してしまいます。ぜひ夫にも同じ方法で対応して欲しいな。
自己肯定感の低い私の活用方法
そして私の最近の活用方法といえば・・・。
自己肯定感が低い自分の特性(周りの人の意見に左右されがち)をしっかり把握して、相手と自分とのあいだに境界線を引いて心が不安定にならないように気を付けています。
まぁ。あまり上手にはできないのですが、母親の心が安定していることが子供にとって一番良いと思うので定期的にこの本を読み返しては軌道修正。
おおらかな母親でいられるように気を付けています。
他にも褒め方に特化したり年齢別だったりといろいろあるので、悩んでいる事によって選んでもいいかも。
その他のおすすめ本はこちら
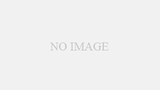
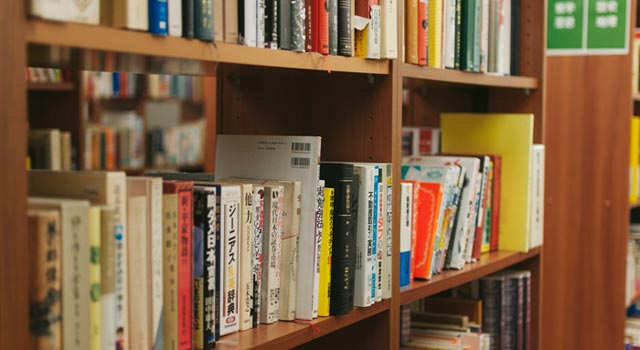






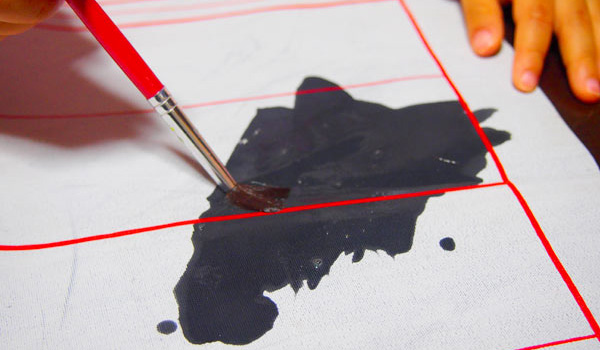
コメント