ちょうど1ヶ月ほど前に「子供の勝ち負けと癇癪とクールダウン」という記事を書きました。

子供がゲームをする際に負けると大泣きして大変だったので、いろいろと原因を考えて対策した記事だったのですが、その後も勝ち負けへの執着はなかなか変わりません。
勝つことへの熱意がすごいです…。
勝ち負けへの執着は消えることがあるのか?
子供は機嫌が悪い時に負けると大変な状態になるため、できるだけ機嫌良く過ごしてもらえるように生活リズムを整えたりしてみましたが、なかなか勝ち負けへの執着は消えません。
というより、ゲームを頻繁にするため、若干強くなっているような…。
ゲームに勝ったり負けたりすることで、適度に負ける経験を積んでくれると思っていましたが、うちの子の場合はそういうのは難しいんじゃないかと感じてきました。
そう思ってネットで「子供の勝ち負けへのこだわり対策」を検索していた時、対処法として「子供が勝つのに飽きて譲るようになるまで勝たせる」というのがありました。
子供が勝つのに飽きて譲るようになるまで勝たせる
ほとんどの場合、子供には「勝っても楽しい、負けても楽しいだよ」と教えると思うのですが、目からウコロです。
- 小さいうちは思いっきり勝たせてあげる
- 勝ち負けに執着しなくなる
- そのうち成長して「今回は相手を勝たせてやるか」という気持ちになる
らしいのです。本当に?
負ける経験を積まなかったら、ワガママでいつまでも勝ちへの執着が消えないんじゃないかと思うのですが、そうでもないようです。
子供はとことん勝つことで勝ち負けへの執着が消えていき、成長とともに負けても大丈夫になるというのです。
確かに、子供の頃に禁止されていたもの(お菓子とかゲームとか)には大きくなってからもずーっと執着する人が多いです。
そう考えると、勝ち続けていればそのうち執着が消えるというのも頷けます。
もしかして、親が勝ち負けにこだわっているのかも?
そうか。飽きるまで勝たせるのか。
負けることに慣れるように適度に負けの経験を積ませようと思って実践していましたが、飽きるまで勝たせるというのはまったく逆の方法です。
親としては「そんなことをして大丈夫だろうか?」とも思います。わがままに育ってしまうんじゃないだろうか…。
そういえば、自分はいつ頃から負けても大丈夫になったかな?と考えたときに、ふと気づいてしまいました。
私も子供と同じような性質を持っています。子供の頃はよく兄弟とゲームをしていましたが、負けて悔しいと泣いた記憶がたくさんあります。
その時、なんとなく気付きました。

あれ?もしかすると自分(親)が勝つことに執着しているのかも。
実は子供のためと言いながら、自分が勝ちたかったんじゃないかな?
子供に負ける経験を積ませたいというのは、もしかして言い訳だったのかもしれません。故意に負けるゲームをやり続けるのにストレスがかかっていたのかも。
そう考えると、なんとなくスッキリしました。私の中にも白黒思考が強くあって、子供相手にも負けたくないという気持ちが無意識にあるのかもしれません。
負けて泣く経験をたくさん積んでも、たぶん勝ち負けへの執着はなくならないのだな。
よし、負けよう。負ける経験を積んでみても勝ち負けへの執着が変わらないなら、今度はとことん負けてみよう。
子供が成長して、小さい子相手に「よし、負けてあげよう」と思えるようになるまで負けてみよう。
新しい勝ち負けへの対処法は「得点表」
今後は勝ち負けのあるゲームには得点表を作り、3回または5回のゲームの合計で勝ち負けを決めることにしました。
負けると決めたけれど、どうやっても配られる手札では勝ってしまうこともあります。
頑張って負けるけどどうしても勝ってしまいそうなゲームでは、得点表を使います。
- 得点表を作る
- 1ゲーム目は必死で負ける
- うっかり勝ってしまったら「得点表では勝ってるよor負けてないよ」とアピールする
- 総得点では必ず負けるように調整する
どうですかね?負けて泣きそうになっても「まだ勝ってるよ!」とか「1対1だね!(負けてないよ)」と言うと、うちの子の場合はぐっと我慢して次のゲームが始められました。
これだと、うっすら負ける体験もできるんですよ!(これでいいのかどうかは謎だけど)
最後に合計で勝てれば癇癪は起こさなくて済むし、私も全てのゲームで負けてぐったりとすることがありません。
最近はどうぶつしょうぎもやっています。子供はすぐ負けそうになるのでアドバイスが欠かせませんが、楽しいです。
うちでは暇だったのでペーパークラフトどうぶつしょうぎを作りました。(ブラザーのプリンタを使ってます)
作るのはすごい大変でしたが、厚紙で作るとかわいいし無料だしでおすすめです。
ただ、収納しにくいので気を付けて…(←収納すると壊れるので仕方なく出しっぱなし)
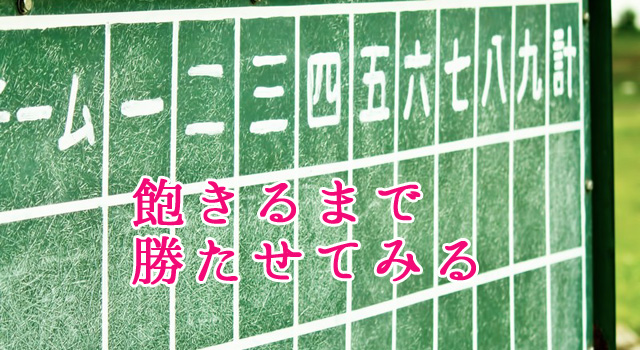



コメント