子供の頃からなんとなくうまくいかない感があったわたし。他の子が簡単にできていることが難しいことが多かったです。
子供ができる前あたりに本で発達障害のことを知りました。あれ?これ、私かも。そんな風に思いました。
人間関係の困り感・・・これって普通なの?
私は子供ながらに偏屈な感じの子でした。本が大好きで親は手がかからないけど、ちょっと何を考えているのかわからない子という感じの扱いでした。
年の近い兄と姉がいたので3番目の私の相手はほぼ姉弟で、親とあまり遊んでもらった覚えはありません。
親は私のことなんか見ていないなと感じていました。
困りごと(1)グループに入っていくのが苦手
昔からグループに入って行くのが苦手であまり人間関係が得意ではなく、いじめられたこともよくありました。
生きづらいなぁと感じ始めたのは小学校の半ばくらいから。グループの輪の中にいてもだいたい外周の一番外側にいる感じです。
イメージとしては、みんな中心を見ているので私のことは見ていません。
困りごと(2)人との繋がりを維持できない
疲れるとそっとグループから離れるけれど、私がいないことには誰も気付かなかったので「私なんていてもいなくても同じだな」と感じていました。
グループのみんなと繋がっている感覚はなく、その中のひとりとやっと繋がっている感じ。その子が抜けるとそのグループには居づらくなるのです。
誰かとふたりでおしゃべりしたり遊んだりするのは好きですが、人が増えるとついていけません。
ついていけないと居心地悪さを感じるし、お友達も楽しそうに見えないのでグループに属しているのが辛くなりました。
ひとりは寂しいけれど人といるのも辛かったので、ひとりでいるようになりました。
困りごと(3)いじめ対象になりやすい
強いタイプの子にはいつも仲間外れにされました。誰かを標的にしてみんなでいじめる人に、すぐ目をつけられるタイプです。
例えば3人仲良しグループで仲間外れにされると、面倒くさいと感じるので自分から離れました。
嫌いなら無理して一緒にいる必要あるのかな。相手から離れにくいなら私が離れておこうと考えるタイプでした。
今でもそういうのは本当に面倒くさいので避けてしまいます。成長していないなぁ・・・。
本の中に困り感を解決する答えを探してみたけど見つからない
本を読むことが好きだったので、自分の感じる「なんだか人と違う気がする」という感覚が何なのか・・・答えを本の中に探しました。
はじめは主人公がいじめを受ける話とか。どんな風に他の人は対処するのか知りたかったんだとおもいます。
どうしてそんなことをするの?とイジメっ子に問いかけるような積極的に解決を図る話は「なんじゃこりゃ。そんなのできない」と思って本を閉じました。
そんなことができるくらいなら悩んでないんだよね。言えないから困ってるんだよね。
自己肯定感が低いとアドバイスが現実的じゃなく感じる
基本的にイジメ関係の本は自分で実践するには難易度が高すぎてダメです。
今考えると、自己肯定感が低すぎるので本のアドバイスを実践できないんですよね。
考え方とか、物事の受け取り方がまったく違うため、アドバイスや解決方法を読んでもピンとこないし、そんな風に考えることができませんでした。
自己肯定感が高い人とは基本姿勢が違うんだなぁ。
なかなか答えが見つからなくてロボットになってた
その頃に私が実践していたのは、自分をロボットだと思って感情を殺してイジメを受け流すという話の本でした。
中学時代はもう、日がな本を読んだりぼんやりとしていたような気がします。
積極的にイジメをしないグループの子に「なにしてるの?」と聞かれたら「・・・光合成」と答えるくらいにぼんやりしていました。
ロボットですとは言えないので、シャットダウンしているときは日向ぼっこしてることにしてたとおもいます。
高校時代は「脳の動きがおかしいのでは?」と疑っていた
高校に入るととても私を気にかけて、かならず手を引いてグループに引っ張っていってくれるお友達ができました。
なんで私のことをそんなに気にかけてくれるのか不思議でしたが、居心地がよくてとても有難かったです。
ただ、この頃に人間関係以外の部分で「あれ?」と思う様になりました。
記憶した内容が一定期間ですぅーっと消えていく感覚がある
本当に記憶力が悪いなぁとは常々思っていましたが、意識して何かを覚えるときに頭の中でスゥーッと消えて行くような感覚があるなと思い始めました。
受験を経て入った学校なのでみんな学力は似たり寄ったりなはずですが、明らかに私は劣っています。
私にできないことをみんながサラッとこなすのを見て、なんだか自分の脳がおかしい気がする・・・と感じ始めました。
感情のコントロールがうまくできない
同時期に、自分自身の感情のコントロールもできないことがあるのに気付いて悩みました。心に波風がたつとうまく処置ができないのです。
感情に引っ張られて爆発してしまい、まわりの人とうまくいかないことがよくあったので、心理系の本を読み漁りました。
トリィ・ヘイデンの本の事例はかなり似ている部分がある
私は物語型なのでトリィ・ヘイデンの本をよく読んでいたと思います。
たくさん子供の事例が出てくるのですが、自分と似たような症状のある子がよく出ています。
後になって考えると、トリィ・ヘイデンの本では情緒障害を持つ子もたくさん出てきます。
結構いい線いってたなとは思いますが、まだまだ「発達障害」とは考えていなくて、「虐待されたことはないしなぁ…」と思っていました。
脳の動きがおかしいならもっと医療系の本を読めばいいのですが、そういうのを読んでもうまく頭に入ってこなくて物語なら読めるのでそういう本ばかり読んでいました。
最終的にうまく当てはまるものを見付けられず「私の脳はポンコツなんだ」と諦めて心理系の本を読むのをやめました。
私は発達障害かもしれない?もしかしたら子供も?
子供ができて、なんとなく子供があまり笑わない感じが気になって育児本を読んでいて発達障害の本を読み漁るようになりました。
育児本でやっと出会えた「発達障害」のこと
子供が生まれるちょっと前に育児本を読んでいて「あれ?この発達障害って私のこと?」とは思ったことがあるのですが、当てはまらない部分も多かったのでそのままになっていました。
発達障害は大まかなタイプはありますが、人によって症状が様々でお医者様でもなかなか判断するのが難しいものです。
ただ、改めてきちんと本を読んで自閉症スペクトラムで納得。これは私のことだ。
遺伝も関係があるということを知り、これはもう子供も持っているかもしれないから真面目に向き合わなきゃと思いました。
発達障害は普通より個性が強い子のこと!と前向きにとらえよう
発達障害は障害という言葉になっているけれど、個性が強い子のことだと(勝手に)思っています。
私がなんとか今まで生きてこられたので、子供も同じように悩んだりしながらなんとか大きくなっていくんじゃないかなぁ。
発達障害という言葉が無かった頃には病気として受け止められていなかったのだし、放っておいてもなんとか生きていくでしょう。
でも、自分が「なぜ?」と本の中に答えを求めてさ迷ったように子供も悩むのなら、ある程度「原因はこれだよ」と教えてあげられればさ迷う時間的ロスは少なくて済みます。
余った時間で対策を考えられる。
ここ数年で発達障害関係の本は爆発的に増えています。情報も探しやすくなりましたねぇ。
それでも発達障害の幅は広いので対応もさまざま。自分や子供に合った内容の本を探し出すのはなかなかに難しいなぁと感じています。
不安強い系の本、おすすめがあったら知りたいです。
★☆ 発達障害関係の本シリーズ ☆★





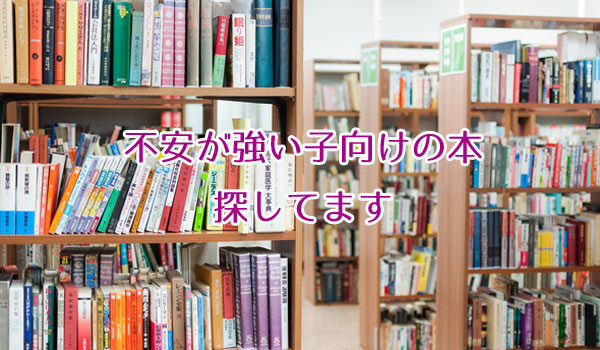


コメント