最近、子供が歌を大声で歌う様になりました。
今までもよく歌ってはいたけれど、現在のように大声ではなかったような。私がいつも車内で好きなCDをかけて歌っているからかなぁ。
困るのは歌う歌が10年以上前の古い歌で彼女が寝ている間に家を出て行く男の歌ってところです。この歌が一番好きなようです。・・・やーめーてー。
子供が失敗したら即座に傍で歌うといい曲
うちの子は所謂「失敗を極端に恐れるタイプ」の子供です。
できなさそうだと思うと絶対にやらないし、一度失敗してしまうと忘れない限りは手を出そうとはしません。
私も子供の頃は似たようなタイプでしたが、年齢を重ねたことで適当を覚えて「ま、いっか」と思えるようになりました。
子供はまだそんなことはなく自分の気持ちに折り合いがつけられずに固まってしまいます。
ここで私はいつも「大丈夫だよ」という風な言葉をかけていたのですが、悲しそうな顔で「もうだめだ・・・できない・・・」とつぶやく子供に、私のかける言葉はあまり届いていないようでした。
ピタゴラスイッチの「がんばれ!装置153番のマーチ」で元気が出る
しかし、先日何か遊んでいて失敗したときに子供が悲しそうな顔をしたので、大好きな教育番組「ピタゴラスイッチ」でデーモン閣下が歌っている「がんばれ!装置153番のマーチ」のサビ部分を歌ってみました。
サビはこんな感じ。
♪しっぱい しっぱい しっぱいのれんぞく
だけど ここで あきらーめるな
子供は途端にぱぁぁぁっと明るい顔になって一緒に歌い始め、そしてもう一度チャレンジし始めたのです。
あ、届いた!それからは何か失敗するたびにこれを歌うようになりました。
何度も何度も失敗しても諦めず、最後はやり遂げるこの歌はすごく子供に勇気を与えるようです。
もう一度やってみて成功することもあれば、何度やってもできなくて結局諦めることもありますが、それでも何度失敗しても次頑張ろうという気持ちになるようです。
閣下、ありがとう!
コツはテンション高く閣下のモノマネで歌うこと
ピタゴラスイッチを見ていない方にはなんのことやらな話なので簡単に説明すると「がんばれ!装置153番のマーチ」というのはピタゴラ装置で失敗したNGシーンを繋げて作られた歌です。
ピタゴラ装置っていつもすごいなぁと思って見ていたけれど、当たり前ですがあんなに何度も失敗を繰り返して作られているのですね。そりゃそうか。一回で成功なんてありえないよね。
こんなに裏で努力し続けてあんなすごい装置を作っているのねと涙が出そうになる歌なのです。
デーモン閣下の渋い歌声が素敵なその歌は、実際に失敗した時に歌うと心の奥底からぬぉぉぉぉ!と勇気が湧いてくるような感じがします。
ぜひテンション高く閣下のモノマネをしながら力強く歌っていただきたい。あらゆる失敗を乗り越える力になると思います。
失敗を恐れる子には「うまくいく方法やコツ」を細かく教える
大人は「失敗してもいいんだよ。大丈夫。」という言葉を子供にかけがちですが、失敗を恐れる子にとってはその言葉はNGなのだそうです。
確かにうちの子にそう言うと失敗することが頭から離れなくなるのか嫌な顔をして絶対にやろうとはしません。
こういう子には「失敗しないための手順を細かく伝える」ことが大切になります。
まず親がやってみせて、手順ややる時のポイントを教えてあげます。不安が強い子供が「よし、やってみよう」と思えるくらい不安を取り除くのが大切です。
こういう子は一度できると「できた!」という気持ちでどんどん上手になります。
「できない」「お母さんがやって!」と言われると逃げてるようで「自分でやりなよ」と言いたくなってしまうけれど、これは子供にとっては困ってる時に自分から「助けて」と言えたという褒められるべきことなんです。
なので「おかあさんやって!」と言われたときは「よし、じゃあ見ててね。これはこういう風にして~」と説明しながらやってみるか、「一緒にやってみようか。手を貸して」と一緒にしてあげます。
やり方を教えたら「よし、もう一度やってみよう」とか「今度はひとりでやってみよう」という風に何度もチャレンジ。
子供が「できたー!」と笑顔になって成功すればしめたもの。めいっぱい褒めて成功体験を積み重ねてあげれば大丈夫。
子供にとって閣下はどんな風に映っているのかな
・・・たまに閣下がニュース番組のコメンテーターとして出ていたり0655でお顔を出して歌っているのを見ます。
私はリアルタイムで聖飢魔Ⅱとして歌う閣下を見たことがあるけれど、子供は閣下のことをどんな風に見ているのかなぁ・・・と子供のほうをチラ見してしまいます。
まだ子供は特に気にはとめていない様子です。
いつか「この人、なんでこんなカッコしているの?」と聞かれたらなんて答えよう・・・。なんだかニヤニヤしてしまうなぁ。
★☆ 子供の失敗したくないおすすめ記事 ☆★



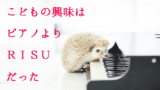
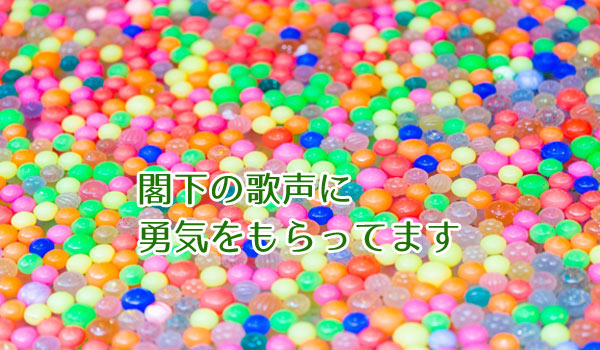


コメント